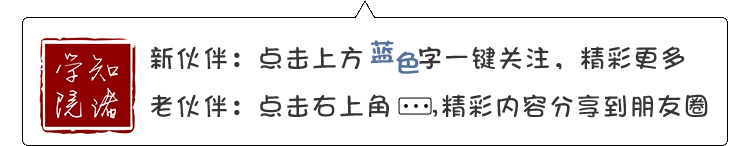
知诸能力考100天计划
【小测验】倒计时第84天
N1小测验
1、この国は、昔から貿易によって
潤って
きた。
1 もうかって
2 まかなって
3 あきなって
4 うるおって
2、警備が
手薄
なところがないか調べた。
1 しゅうす
2 しゅはく
3 てうす
4 てはく
3、この連載小説は全12話で( )する。
1 静止
2 成就
3 完結
4 終息
4、会議で質問に答えられなくて困っていたら、課長が( )してくれた。
1 キープ
2 フォロー
3 マッチ
4 アップ
5、彼はお金に関して
ルーズ
なところがある。
1 ずうずうしい
2 だらしない
3 うるさい
4 よわい
6、この職場にもかなり
なじんで
きた。
1 恵まれて
2 逆らって
3 飽きて
4 慣れて
7、 発足
1 これから、先日
発足
した問題について検討しましょう。
2 新技術を
発足
したおかげで、他社との勝負に勝った。
3 この団体は先月
発足
したばかりです。
4 この出版社は、来月、新しい週刊誌を
発足
する。
8、 にぎわう
1 朝の電車は会社に行くサラリーマンで
にぎわって
いる。
2 休みの前の日の夜は、どこのレストランも
にぎわう
。
3 都会の真ん中にあるこの公園は、いつも緑で
にぎわって
いる。
4 この図書館には、いろいろな分野の本が
にぎわう
。
9、A社の元社員が11日、突然の解雇を不当( )、解雇取り消しを同社に求める訴えを起こした。
1 となって
2 になって
3 として
4 にして
10、下水道工事中、ご不便をおかけ致しますが、どうかご理解( )、よろしくお願い申し上げます。
1 いたしたく
2 いただきたく
3 差し上げたく
4 申しあげたく
11、
A「申し訳ない。僕が
★
ことになってしまって。」
B「あ、いいえ、気にしないでください。」
1 残業してもらう
2 君にまで
3 ミスをした
4 ばかりに
「あの人は、私が話し始めて一分とたたないうちに、話題を自分の話にすりかえてしまう」と言われる人のなかには、決して聞き上手ではないけれど、不思議と嫌われない人がいる。
話を奪われた人も、「私の話よりずっとおもしろそう。私の話が宙に消えて(注1)もしょうがないか」という寛容な気持ちになるのだろう。
もちろん、私は「だから、話上手になればいいんですよ」とは言わない。ただ、「聞き上手でないことが帳消しになるほど話上手な人のしゃべりは、ちょっと研究してみる価値がありますよ」とご提案したい。
聞き上手になるための「修業」(注2)をしていると、そのうち話の上手な人の特徴がわかってくると思う。
聞き上手から、話上手でもあるというプラスアルファの魅力を持つ人間へとステップアップする(注3)には、いつの間にか相手を自分の話に引きこむのが上手な人の話ぶりを、「それはなぜなのか」と自分なりに分析すると、とても勉強になるのだ。
一人で分析するのが難しければ、だれかに「あの人は話が上手だよね。どんな話しぶりに惹(ひ)かれる?」と疑問をぶつけてみるのもいい。
その勉強の成果は必ずや、自分の言動に投影されるはずだ。だれだって、他人のいいところは真似(まね)したいと思うから。
(斉藤茂太『どんなグズもなおる本-17タイプ別グズ解消法』による)
(注1)話が宙に消える:話が途中でどこかへ行ってしまう
(注2)修業:学んで身につけること
(注3)ステップアップする:進歩する
12
寛容な気持ちになる
とあるが、なぜそうなるのか。
1 相手の話が自分の話よりおもしろくて引きこまれてしまうから
2 話を奪ってしまった人の態度が堂々としていて魅力的だから
3 自分の代わりに話上手な人が話をしてくれれば助かるから
4 相手は確かに話上手だけれど、聞き上手とは言えないから
13 話上手になるにはどうすればいいと筆者は述べているか。
1 話上手な人になぜ上手なのかと尋ねて分析する。
2 どんな話題でも自分の話にかえられるようにする。
3 人の真似(まね)をしないで、聞き上手になるための研究をする。
4 話上手な人をよく観察して、その特徴を自分のものにする。
14 筆者の考えと合っているのはどれか。
1 聞き上手になるだけでなく、話上手な人にも学んでみるとよい。
2 聞き上手は損をすることがあるので、話上手になったほうがよい。
3 他人に嫌われないように、話上手より聞き上手になったほうがよい。
4 聞き上手から話上手になるには、自分の話し方を分析してみるとよい。
ツバメは季節の変化にあわせて、くらす場所をかえる渡り鳥です。日本が冬の時期は、暖かくてえさの豊富なオーストラリアや東南アジアでくらしています。たまごを産んでひなを育てる繁殖期が近づくと、春になってえさとなる昆虫が一気にふえる日本へ向けて、いのちがけで海を渡ってきます。
ツバメの渡りは地球の南半球から北半球へと、何千キロメートルにもなります。ツバメがいつ渡ってきたかで、ツバメがくらしていた地域や、渡りのルートの気象の変化や環境の変化をおしはかる(注) ことができます。そして、その変化を長期間にわたって観察をつづけることで、地球全体の気象の変化を予測する手がかりにもなるので、気象庁では、その年にはじめてツバメを見た日「ツバメの初見日」を、各地の観察者や研究者からの報告をもとに、記録をとっているのです。
ツバメが渡りの行動をおこすのは、日照時間にかかわりがあるといわれています。(中略)
日照時間は年ごとの変化が比較的少ないので、日時がそれほどずれることがありませんでした。ところが長年蓄積された記録を調べてみると、近年、各地のツバメの初見日が早まってきていることがわかってきました。
その原因は……。
まだはっきりとつきとめられてはいませんが、地球温暖化によっておこる気象の変化で、オーストラリアや東南アジア地方の晴、雨天のバランスがくずれ、日照時間にまでくるいがでてきているのかもしれません。
(七尾純『テクテク観察 ツバメ日記』による)
(注)おしはかる:推測する
15 ツバメが日本へ渡ってくるのはなぜか。
1 南半球でひなが育ち、えさとなる昆虫が不足するから
2 日本が春になる頃、ひなが海を渡れるようになるから
3 日本が暖かくなるとえさがふえ、子育てがしやすいから
4 日本は冬になっても、他の地域より暖かくえさが豊富だから
16 「ツバメの初見日」を記録しているのは何のためか。
1 ツバメの渡りのルートを解明するため
2 日照時間の短縮の原因を究明するため
3 世界の気象や環境の変化を研究するため
4 観察者や研究者に気象情報を提供するため
17 最近の「ツバメの初見日」と日照時間の関係について正しいものはどれか。
1 南半球などで日照時間に変化がおきてツバメの渡りが早まっているのだろう。
2 温暖化で日本の日照時間が長くなり、ツバメの渡りが遅れてきているようだ。
3 ツバメは毎年日照時間と関係なく渡りを始めるようになったのかもしれない。
4 日本の日照時間にくるいがでたために、ツバメが早く渡ってくるようになった。
清森市 秋の美術コンクール
作品募集
部門
絵画部門、写真部門
募集期間
2010年11月1日~11月30日
審査員
山田太郎(日本アート協会会長)、山本花子(画家)、川上次郎(写真家)
応募規定
1 清森市内の秋を題材にしたもの。
2 絵画部門に出品する作品は、イラスト、水彩画、油絵、どれでも可。
写真部門に出品する写真は、フィルム写真、デジタル写真、どちらも可。
※応募作品は各部門1人1点に限ります。
※作品の制作年は問わないが、未発表のものに限ります。
(他のコンクールに入賞していたり、出版物や展示会などで公表されたりしていないものであること。)
応募方法
郵送、または持参。ただし、郵送中の事故について、市は責任を負いません。
指定の応募用紙を作品裏側に添付のこと。応募用紙は市役所の窓口で、または市のホームページ(http://www.kiyomori-shi.jp)から入手可能。
応募先
清森市商業観光課観光係
(〒951ー0022 清森市清森2ー8 TEL084ー874ー8524)
|
最優秀賞
|
各部門1点
|
賞状と副賞(デジタルー眼レフカメラ)
|
|
優秀賞
|
各部門2点
|
賞状と副賞(清森ホテルのペア宿泊券)
|
|
清森賞
|
各部門20点以内
|
賞状と副賞(図書カード5千円分)
|
審査結果
清森市のホームページ上に1月15日に発表します。入賞者には1月中に結果を郵送します。電話および窓口での問い合わせには応じられません。
表彰式
2011年2月下旬(予定)最優秀賞と優秀賞の方には、表彰式で賞状および副賞をお渡しします。
注意事項
※入賞作品は、1年を限度に主催者がお預かりして広報活動などに使用し、1年後にお返しします。
※上記の応募規定を守っていなかった場合には入賞が取り消されることがあります。
〈主催〉 清森市 〈協賛〉 昭和デザイン株式会社、山手百貨店、新東京鉄道、清森ホテル
18 高木さんが制作した以下の作品のうち、応募できるものはどれか。
1 清森高校に通っていたとき入賞した秋の風景画。
2 清森市にある清森温泉の紅葉の油絵とイラスト。
3 清森市にある清森公園で撮った春の木々の写真。
4 去年清森市で行われた秋祭りの写真と水彩画。
19 入賞したかどうかを知るには、高木さんはどうしたらよいか。
1 1月中旬に清森市のホームページを見る。
2 1月中旬に直接、観光係に電話して聞く。
3 2月下旬に市役所の窓口に問い合わせる。
4 2月下旬に届く予定の通知を待つ。
20
听力音频:
1 原材料の写真を使用する。
2 キャラクターの絵を使用する。
3 生産地の写真を使用する。
4 商品名を真ん中に移動する。





