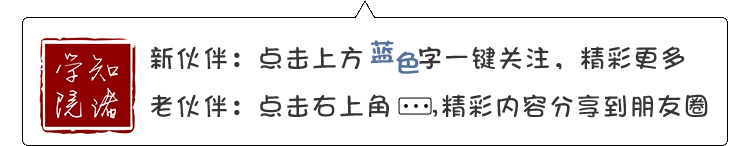
知诸能力考100天计划
【小测验】倒计时第84天
N2小测验
1 晴れている日は、この山頂からすばらしい景色が見える。
1 けいしき
2 けしき
3 けいいろ
4 けいろ
2 このお金は、何かあったときに備えて残しておこう。
1 ととのえて
2 たくわえて
3 かかえて
4 そなえて
3 夏休みに旅行に行きたいので、( )収入のアルバイトを探している。
1 上
2 良
3 優
4 高
4 来週の会議には、社長と( )社長も出席する予定だ。
1 準
2 副
3 補
4 助
5 疲れると、集中( )が落ちて仕事が進まなくなる。
1 能
2 考
3 気
4 力
6 彼はとても
れいぎ
正しいです
。
1 札義
2 札儀
3 礼義
4 礼儀
7 彼は苦労を重ねて、社長にまで
しゅっせ
した。
1 出成
2 出世
3 昇成
4 昇世
8 今日の講演のテーマは、教育の( )問題についてです。
1 諸
2 複
3 雑
4 類
9 駅前の商店( )で、買い物して帰ろう。
1 帯
2 域
3 街
4 町
10 きっかけ
1 季節の
きっかけ
は風邪をひきやすい。
2 友人に写真をほめられたのが
きっかけ
で、本格的に勉強を始めた。
3 その意見に反対する
きっかけ
は、主観的すぎるからだ。
4 今回は時間がないので、次の
きっかけ
に訪れようと思う。
11、
A「先週の授業、どこまで進んだ?」
B「3課の文法の練習問題を
★
終わったよ。」
1 で
2 解いた
3 ところ
4 まで
①会話の技術は、運転技術とよく似ています。
ボーッと運転をしていると、事故を起こしかねません。たとえば、数人で楽しく盛(も)り上(あ)がっているときに、いきなり入ってきて、自分の話を始める人がいます。あれは、高速道路に加速しないで進入してくる車のようなもので、本人は気づかなくても、入った途(と)端(たん)にクラッシュし
(注1)
ているのです。
グループに加わりたいときは、まず黙(だま)って話を聞くことです。
②うなずきながらエンジンを温め
、他の車と速度を同じくして会話に加わると、流れにうまく乗ることができます。
そのうえで、自分の話ばかりしないように注意すること。人は誰(だれ)でも、自分の話をしたがっているのですから。会話は、ボールゲームのようなものです。サッカーでもバスケットボールでも、ひとりでボールを独占していたら、次からは遊んでもらえなくなります。
みんなで話しているとき、自分がどれだけ話をしたのか、常に意識していることも必要です。特に、大勢で話しているときは、発言しない人により多くの意識を配ってください。おとなしい人は無視されがちですが、同じ場にいることに敬意を払って、その人にも話を振ら
(注2)
ないと。
つくづく思いますけれど、会話ほど、個人のレベル差が大きいものはありません。充実した会話をしたいのであれば、それなりの準備や練習は必要なのです。私は練習することで得るものは大きいと思いますよ。その中に、人生を変える出会いや幸運が潜(ひそ)んでいる
(注3)
のではないでしょうか。
(斎藤孝「できる人」の極意!による)
(注1)クラッシュする:衝突事故を起こす
(注2)話を振(ふ)る:話す機会を与える
(注3)潜(ひそ)んでいる:隠れている
12
①会話の技術は、運転技術とよく似ています
とあるが、この文章ではどんなところが似ていると述べているか。
1 運転で他の車に注意が払える人は会話でも他者に敬意が払えるところ
2 会話も車の運転も技術が高ければ仲間と楽しい時間を過ごせるところ
3 会話も車の運転のように他者とペースを合わせることが求められるところ
4 車の運転で事故を起こさない人は会話も同じように慎(しん)重(ちょう)に進められるところ
13
②うなずきながらエンジンを温め
とあるが、ここではどういうことか。
1 人の話に軽く返事をしながら車のエンジンを温めること
2 自分の話を聞いてもらいながらグループの話も聞くこと
3 まずは人の話を聞きながら会話に加わる準備をすること
4 静かに自分の話しをしながら次の話題に移るのを待つこと
14 みんなで会話をしているときには、どのような注意が必要だと述べているか。
1 自分の発言量を意識しながら、おとなしい人にも話してもらうようにすること
2 発言が少ない人やおとなしい人の話をよく聞き、それに答えるようにすること
3 ふだん発言しない人も、みんなの話をよく聞いて会話に参加するようにすること
4 おとなしい人も、大勢で話すときは意識して他の人に話しかけるようにすること
2000年から2001年にかけて、全国紙として有名な新聞が、基本の活字を少し大きなものに変えました。地方紙も同じだったと思います。高齢者人口の増加が原因でしょうが、新聞を読む人の総数の中で、老(ろう)眼(がん)鏡(きょう)
(注1)
を必要とする人の割合が増えたからです。
新聞だって「お客様は神様」でしょうから、その「神様」のニーズに沿って紙面を変えるということは、とうぜんのことです。その案内の記事では、これまでの活字と新しい活字を比較して、いかに見やすくなったかがしめされていて、わかりやすく納得できるものでした。そして、各社ほとんど同じことを書いていたと思いますが、紙面の大きさは変えないわけだから、「文字が大きくなった分、文字数を減らさねばなりません。そこで、記事は要点をおさえ
(注2)
、簡略化して適切化をはかる
(注3)
」というような説明になっていました。なるほどと思う一方、①
これまではそうでなかった
のかなとも思いました。
大きな活字の本も出まわるようになってきました。とくに辞書は同じ内容で同じデザインで大きな版
(注4)
のものが出て、老(ろう)眼(がん)鏡(きょう)なしでも利用できるとありがたがられています。ただサイズが大きくなった分、大きく重いという欠点もありますが、その快適さに換えられないという人には②
問題になりません
。
(光野有次『みんなでつくるバリアフリー』による)
(注1)老(ろう)眼(がん)鏡(きょう):年をとって近くが見えにくくなった人のための眼(め)鏡(がね)
(注2)要点をおさえる:要点をつかむ
(注3)適切化をはかる:適切になるようにする
(注4)版(はん):ここでは、サイズ
15 新聞の文字が大きくなった理由は何か。
1 文字を大きくすることで要点がわかりやすくなること
2 小さい文字が読みにくい高齢の読者が多くなったこと
3 紙面に余裕ができるように記事の表現を簡略化したこと
4 高齢者から情報を絞ったほうがよいという意見があったこと
16 ①
これまではそうでなかった
とは、どういう意味か。
1 以前の紙面は活字の大きさを内容ほど重視していなかった。
2 以前の紙面は高齢の読者のニーズに十分こたえていなかった。
3 以前の紙面は重要な情報が簡潔にまとめて書かれていなかった。
4 以前の紙面は読者が納得できるほど詳しく説明していなかった。
17 ②
問題になりません
とあるが、何が問題にならないのか。
1 本を軽くするために活字が小さくなったこと
2 老(ろう)眼(がん)鏡(きょう)を持っていないと少し読みにくいこと
3 活字が大きくなって情報が少しだけ減ったこと
4 文字が拡大されて辞書が以前より重くなったこと
A
社内にばかりいると、ビジネスマンとして人脈(じんみゃく)
(注1)
も広がらない。そこで、セミナーや勉強会、講演会などに出かけて自己を磨(みが)いている人も多いはずだ。しかし意外と、あまりメモもとらず、「聞きっぱなし」という人も多いのではないだろうか。
話を聞いているときは「なるほどなあ」と思っていても、それを的確にメモしてなければ、あとになって「あの話は何だったっけ」ということになる。人間は忘れやすい動物なのだ。
では、こういうときのメモはどうすればいいか?
基本的なことは、話の内容をいちいちすべてメモしまい、ということである。漫(まん)然(ぜん)と
(注2)
聞いて、話したことをすべてメモしていたら、核(かく)心(しん)
(注3)
が見えなくなる。そこで、自分の仕事やライフスタイルに関係すること、本当に興味のあることしかメモしないのである。
(坂戸健司『メモの技術』による)
B
昔、ある大学者が、尋ねてきた同(どう)郷(きょう)
(注4)
の後輩の大学生に、一字一句教授のことばをノートにとるのは愚(ぐ)だ
(注5)
と訓(おし)えた。いまどきの大学で、ノートをとっている学生はいないけれども、戦前の講義といえば、一字一句ノートするのは常識であった。教授も、筆記に便なように
(注6)
、一句一句、ゆっくり話したものだ。
その大学者はそういう時代に、全部ノートするのは結局頭によく入らないという点に気付いていたらしい。大事な数字のほかは、ごく要点だけをノートに記入する。その方がずっとよく印象に残るというのである。
字を書いていると、そちらに気をとられて、内容がおるすになりやすい
(注7)
。
(外出滋比古『思考の生理学』による)
(注1)人(じん)脈(みゃく):人のつながり
(注2)漫(まん)然(ぜん)と:あまり注意しないで、なんとなく
(注3)核(かく)心(しん):一番大切な部分
(注4)同(どう)郷(きょう)の:同じ出身地の
(注5)愚(ぐ)だ:ばかだ
(注6)便なように:便利なように
(注7)内容がおるすになりやすい:内容に注意が向かなくなりやすい
18 Aは、なぜメモをとることを勧めているのか。
1 話の内容を忘れないようにするため
2 話の内容に集中できるようにするため
3 話の内容に興味が持てるようにするため
4 話の内容を聞き落とさないようにするため
19 AとBで共通して述べられていることは何か。
1 メモやノートに話の内容のすべては書かないほうがよい。
2 聞いたことをすべてメモやノートに書くと記憶に残りやすい。
3 印象に残ったことだけを後でメモやノートにまとめるとよい。
4 メモやノートを的確にとれば話に関心が持てるようになる。
20
音频:
1 医者に吸うなと言われたから
2 身近な人にめいわくがかかるから
3 吸えない場所が増えているから
4 たばこが値上がりしているから





